
実は学校推薦型入試で国立大学を受験した娘、推薦合格をいただきました。
上の子は後期試験まで引っ張ったので、1ヶ月半も早く終わる受験のありがたさに泣いてます…。
共通テストが終わり、判定が出てから怒涛の出願。
国立大学は、共通テスト利用型の学校推薦型入試・前期・後期の3つ。
すべり止めの私立大学は、2学科をそれぞれ一般入試と共通テスト併用型で合計4つ。
このうち、共通テスト→私立①→学校推薦型入試→合格通知ということになり、私立②以下は受験する必要がなくなりました。
もちろん、試験料は返ってきませんがね。
全然いいんですぅ~♪
もし推薦が不合格だったら、同じ大学の前期試験に願書を出していたのでそこで挑戦する予定でした。
国立大学の推薦は合否確率は半々ぐらいですが、一般入試で再チャレンジすることができます。
どこの大学もそうなのかはわかりませんが、娘が受けた大学は、出願倍率や過去の合格者水準から推定すると、もし推薦でダメでも前期ならいけるでしょうという状況でした。
なので、推薦入試を受けた後も粛々と前期試験の勉強を続けていました。
わたしが合格を知ったのは、発表当日の仕事の昼休みにLINEを開けた時。
娘から合格したとメッセージが入っていて、HPで受験番号が載っていることを確認すると、うれしくてうれしくて午後の仕事はあっというまに終わりました。
帰りにちょっと高級なスーパーでお寿司や総菜、スイーツなどを爆買い(といっても5千円ぐらい)して、親子3人でお祝いしました!
前期と後期の試験のために予約していたホテルもキャンセル。
ええ、旅費もかからずにすみましたよ。
なによりも大きいのは、私立大学の入学金を払う必要がないことです。
私立大学の入学金は、合格発表のあと、国立大前期の合格発表の前に入金締切日が設定してあります。
25万円ぐらいかな?それがいらないわけです!
上の子の時に、行かないかもしれないのに私立大の入学金の支払いがきついと職場の先輩ママに愚痴ったら、
「うちなんか私立全落ちして国立大入試にのぞんだのよ!
お金さえ払えば行ける権利もらえるなら喜んで払いたい気分だったよ!」
とはげまされたこともありました(汗)
けどね、推薦入試で早く決まると、その支払いすらしなくてもいいんですよ。
世の中にはこんなにオトクな経験をしている人がいたんだね、と2人目の子どもにしてはじめて体験しました。
まわりで、推薦で国立大に合格した話を聞いて、どうしたらその権利を得られるのだろう?と疑問に思っていましたが。
上の子の時は、希望する大学の学部では推薦入試を採用していなかったり、学校推薦の成績基準を満たしていなかったりで、まったく縁がありませんでした。
下の子は評定がよかったので高2ぐらいから、
「どこかに推薦してもらえるのでは…」
と思い始め、三者面談のたびに先生に相談を始めました。
高2の夏に塾に入ると、塾からも「推薦入試をねらうのもいいのではないか」とアドバイスをいただき。
しかし、最初は娘は推薦入試に乗り気ではありませんでした。
推薦入試対策もたいへんだし、かといって合格するかもわからないし、そのせいで一般入試対策も不足してしまったら怖い、という不安で。
そんな時、その当時娘が希望していた大学へママ友のお子さんが推薦で合格していたことを思い出しました。
なので母同士だけですが、会って話を聞くと、やはり推薦もらえるならぜったいいいよ!とおすすめされました。
その後、塾を辞めると同時期に希望大学が変わりましたが。
総合選抜型・学校推薦型Ⅰ・学校推薦型Ⅱの3つの推薦入試を採用している学部を希望したので、どれを利用するか担任と相談して決定。
共通テスト利用型の学校推薦型Ⅱに決めたので、これまでどおり共通テストの勉強を進めて、自己採点の結果いけそうだと判断できたので、まずは推薦へ願書提出。
ただしこの時、推薦入試の前に前期と後期の願書も提出する必要はあります。
共通テストから推薦入試までには、二次試験の勉強と並行して、推薦入試の面接指導を学校でやってもらえました。
私立大学の受験勉強は入試の数日前に過去問を解く程度で、ほぼ二次試験対策をしていたようです。
そういう生活が共通テストから3週間ほど続き、推薦入試~その一週間後に合格発表という流れでした。
とってもうれしいのですが、親がその後にしなければいけないことが山ほどあって、何か抜けていたらと思うと気が張る日々が続きました。
締め切り日があるやらなきゃいけないことは現在進行中ですが、やっと一段落してブログを書くことができています。
手続きやらもろもろの話は、また次回に。










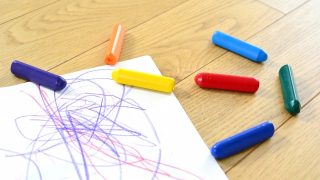










コメント